小場 恒吉 (おばつねきち)
文様学の権威
2014年02月14日更新
おばあちゃん子
明治十一年(一八七八)一月二十五日に秋田市中通(旧亀ノ丁堀反町)で呱々の声をあげた小場恒吉は、少年時代から野山に出かけて露草などを摘み、それを揉んでは紙になすりつけ色具合などを楽しんでいたという。後年の小場の活躍を予想させるエピソードである。
小場家は佐竹家の一族を成す名家で、秋田藩の家老職である寺崎家、疋田家などとも血縁関係にある。
恒吉の父親の新吾は秋田が誇る江戸時代の能書家・石田無得の書を学んでおり、芸術の理解者でもあったが、恒吉の誕生後まもなく他界している。
母親がやがて再婚して恒吉は義父を迎えるが、もっぱら祖母の手によって育てられ、恒吉はおばあちゃん子として成長した。
十歳のころ、秋田の有名な画人であり親戚でもあった小室怡々斎(いいさい)に師事し、早くも狩野流の絵の手ほどきを受けている。
学校の方は、明治三十一年に秋田中学を卒業すると同時に官立東京美術学校(東京芸術大学美術学部の前身)の日本画科に進む。当時、美校では秋田の先輩であり、親類筋にもあたる日本画家の寺崎広業が教鞭をとっており、小場としてもこころ強いものがあった。
ところが、当時、美校では既述のように岡倉天心校長に対する排斥運動が起こっており、この騒動によって天心は美校を去ることになる。頼りにしていた広業も校長に殉じて去って行ったので、小場のこころには大きな空虚感が広かった。
一方、小場には老いた祖母の面倒を見なければという使命感があり、それには日本画科で学ぶよりも図案科に移った方が、将来の生活という点では不安が少なかったし、直接の恩師今泉雄作の膝下で薫陶を受けたいという気持ちもあった。
それやこれやで小場は本科一年の時に図案科に転科するが、この転科は、結果的に小場の人生に決定的な意味をもつことになった。
明治三十六年、小場は図案科建築装飾部の最初のしかもたった一人の卒業生として美校を卒業する。卒業作品は「美術学校設計図」で、これは、中央の巨大なドームと四隅のドームで構成された、ルネサンス式総合様式からなる近代的建築の設計図であった。
東洋のそれも古い時代のものを対象にして数多くの大きな仕事をした後年の小場からはちょっと想像できないが、斬新さという点でも人後に落ちないということの一つの証明であろう。
美校卒業後、小場は一時、茨城県の竜ヶ崎中学に就職するが、祖母のことが気になって帰郷し、三十九年四月九日から四十年十二月二十七日まで県立秋田工業学校(現秋田県立秋田工業高校)に勤務する。現在も用いられている同校の校章は、在職中に小場がデザインしたものであった。
小場と祖母の恩愛のきずなは、後年、小場が自分の長女にカネという祖母の名をもらって命名するほど深いものであった。
並々ならぬ筆力
四十一年、小場は母校である美校の図案科助手として迎えられ、再度上京する。美校在学中に、東大寺三月堂諸仏像装飾文様(天平様式)と宇治平等院鳳凰堂装飾文様(藤原様式)の模写で顕著になった小場の並々ならぬ才能が改めて評価されたのである。
助手として美校に戻った小場は、筆力にまかせ、あらゆる絵の模写を手がける。狩野派、四条派、さらには大和絵も描くなど精力的に仕事を展開した。
助手時代の四十一年から四十四年にかけては、文様関係では以下の模写を次々に手がけ、後世に貴重な資料として残した。
- 宝生寺仏光背装飾文様(弘仁様式)
- 興福寺三重塔背堂装飾文様(鎌倉様式)
- 薬師寺東塔装飾文様(藤原様式)
- 醍醐寺五重塔装飾文様(藤原様式)
- 栄山寺八角堂装飾文様(天平様式)
- 法隆寺百済観音光背装飾文様(推古様式)
- 法隆寺玉虫厨子装飾文様(推古様式)
- 薬師寺四天王装飾文様(足利様式)等
大正元年(一九一二)、小場は東京美術学校の助教授に昇進して工芸史、文様史を担当する。
その年の夏、朝鮮の江西(平壌=ピョンヤンの近く)にある二大高句麗古墳壁画の模写を委嘱され、小場は、勇躍朝鮮に渡った。日本の文様を幅広く模写・研究していくうちに、どうしても朝鮮、中国の古美術を自分の目で調査する必要を痛感するようになっていたからである。
朝鮮の古墳壁画は想像していた以上に芸術性の高いもので、小場は翌二年、翌々三年にも渡鮮、江西付近の塚で壁画の模写に打ち込み、ついには、朝鮮で徹底的に研究するため、美校助教授の地位をなげうち、当分の間朝鮮で暮らすことを決意する。
具体的には朝鮮総督府のもとで研究に従事することになったのだが、発掘の現場は清潔な水もなくて悪疫が多く、時には絵の具も凍るほどの寒さになったり匪賊が出没するようなこともあって仕事は困難を極めた。
しかし、小場は、何枚もの鏡を利用して大陽光線を暗い古墳内に導き入れる工夫をするなど、あくまで自然光を用いて模写することに全力を傾けたのであった。
小場が師と仰いでいたのは、郷土の先輩で東洋史学の権威である内藤湖南京都帝国大学教授である。朝鮮での調査研究も陰陽両面からの内藤博士の支援があって進めることができたのである。師が師だけに、小場の学識も他を圧しており、内藤博士の没後は、中国の古代文字をすらすら読めるのは小場ただ一人と評されたのであった。
小場は昭和七年(一九三二)から、新羅の旧都慶州における仏跡調査を行い、十六年には豪華な調査報告書『慶州南山の仏跡』を刊行した。それは、同十年刊行の調査報告書『楽浪王光墓』とともに、小場がこの世に残した数少ない格調高い研究書として珍重されている。
秋田市の市章を考案
小場は、大正十四年から講師として再び美校の教壇に立つ。ボソボソした秋田弁ながら、その内容は実に名講義であったという。
時間になって教室に現れると、自分で実測した古美術の精巧な青写真をまず学生に配り、その後ボロボロのノートを取り出して講義に入る。克明に書き込んだノートは研究が進むごとに細かく加筆され、学問に没頭している小場の面目が躍如とした美校の名物ノートだったらしい。
また、学生に興味を持たせるため、黒板に漢時代の馬を描く場合などにも、頭の先とか尻尾とかとんでもないところから始め、何を描いているのだろうと、描き終わるまで学生の首をひねらせるといった工夫もしていたという。
学生の他、一般の画人が小場のもとを訪れては、彼から専門的な示唆を受けることも多かった。同郷の日本画家平福百穂などもその一人である。百穂の「丹鶴青瀾」「荒磯」などの作品は、小場から紹介された高句麗の壁画をヒントにして、百穂独特の波を描き出したものだと言われている。
故郷秋田との関係では忘れられないことがもう一つある。現在用いられている秋田市章が小場の考案になるものだということである。
昭和三年(一九二八)は、秋田市に市制が敷かれて四十周年に当たっていた。その記念の一つとして市の紋章を定めることになり、その考案者に小場が擬せられたのである。
よろこんで引き受けた小場は、久保田城のあったいわゆる矢留の森(千秋公園)の「矢留」と「秋田」をモチーフにして、的に矢を配した簡潔なデザインにまとめ上げたのであった。ただし、配色は今とは逆で、紺地に白抜きであった。
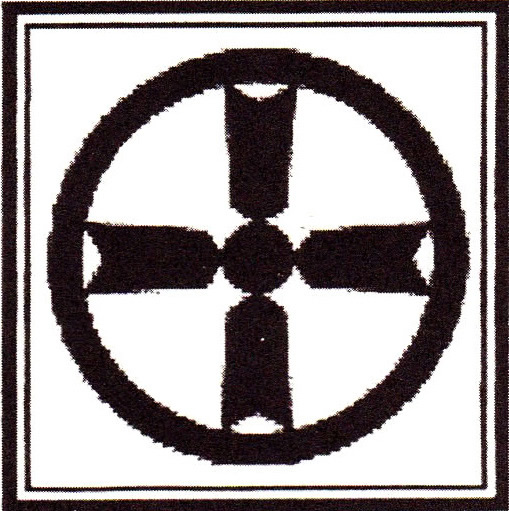
小場が考案した秋田市の市章
この市章が正式に認められたのは六月八日の市議会の場においてだが、それに先立つ五月二十九日、平福百穂から井上広居市長にあてた手紙の中で、「小場君御考案の徽章拝見。誠に申し分なき理想的のものと存じ候」と、評価されている。
また、千秋公園にある佐竹義堯公の銅像は、大正四年に東京美術学校の教師たちによって製作されたものだが、銅像は高村光雲、像原型を白井雨山、総合設計を小場が担当したものである。
その銅像が戦時中に供出され、台座のみ空しく風雨にさらされていたのを、戦後の昭和二十五年、小場が新たに設計、原型の小さい像を新羅風の厨子に入れるという日本の伝統に則ったつくり方で、面目を一新したものである。旧藩主につながる仕事のこととて、小場もこの事業にはことさらな思いをもって携わったようであった。
なお、現在の銅像は、平成元年(一九八九)、秋田市が市制百周年を記念して復元したものである。
芸術院恩賜賞受賞
昭和ニ十四年、小場は東京芸術大学の教授に昇進すると同時に法隆寺五重塔本尊舎利容器調査委員にも任命され、翌二十五年には記念すべき第一回目の日本芸術院恩賜賞を授与される。
芸術院による授賞理由書には、「小場恒吉氏の研究は、日本文様の時代的特徴と変遷を解明したもので、この道は学者と同時に技術家でなければよく実態を把握し得ない分野である」と述べられている。一般の美術史家と異なり、小場は絵画の手腕と製図技術に卓越していたのである。
だからこそ、古壁画の現状模写においても復元模写においても、見る者の目を見張らせるような華麗な美の世界を再現させ、貴重な資料として後世に残すことが可能になったのであった。
小場の芸術院賞は第一回目であったため前例がなく、しかも受賞者が文様学の大家であることから、その賞牌の製作には大変な神経と五年の歳月が費やされたことがエピソードとして語り継がれている。
なお、小場は昭和三十年に紫綬褒章を授与されているが、これには長男を代理出席させた。芸術院恩賜賞を受けた後なので、なにを今さらという気持ちがあったのかもしれない。
昭和ニ十七年、小場は七十四歳で東京芸術大学を退官する。退官後は思い出の地である関西をしばしば訪れ、二十九年から三十一年にかけて、宇治平等院鳳凰堂装飾文様の現状模写と復元模写に従事している。
この仕事のために出張してくる小場を出迎えるべく京都府の関係者が宇治駅に出向いたが、いくら待っても小場が下りてこない。実は、普段から蓬髪、着流しで服装などには一向にこだわらない小男の小場が、この日も浴衣に下駄履きという姿でさっさと通り過ぎた後だったのである。
仕事となると鬼と化する小場だが、日常は無為自然を旨とする荘子の思想をよしとして世俗的栄誉にこだわらず、いつも恬淡としてわが道を行く趣きがあった。
小場が脳軟化症を患い、八十歳で逝ったのは昭和三十三年五月二十九日だが、遺言により僧侶は招かず、自筆の平等院鳳凰堂南画扉絵(下品上生来迎図)一幅を掛けただけの、いかにも小場らしい簡素で清々しい葬儀が営まれ、遺骨は、代々の先祖が眠る秋田市の禅光明寺の墓地に納められた。
戒名の「文昭院常恒顕彰大居士」は、法隆寺の佐伯良謙管長から贈られたものである。
- 15 小場恒吉.pdf (2931.8kb, application/pdf)
- 15 小場恒吉.docx (176.6kb, application/vnd.openxml…)


